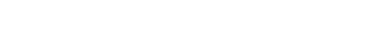【経済安全保障】
1.『経済安全保障推進法』(2022年5月12日成立)に基づく「サプライチェーンの強靱化」に関する制度
(経緯)
- 2022年9月30日 『特定重要物資の安定的な供給の確保に関する基本指針』閣議決定
- 2022年12月23日 半導体、蓄電池、肥料、抗菌薬など11物資を「特定重要物資」に指定する『経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(政令)』を施行
- 2024年2月2日 先端電子部品やウランを「特定重要物資」に指定・追加する『政令』を施行
- 2024年8月31日現在 計91件の「供給確保計画」を認定
(概要)
- グローバリゼーションの進展を背景とした供給網の多様化が進む中で、各国で供給ショックに対する脆弱性が増大している。国民の生命、生活や経済上重要な物資を他国に依存した場合、他国に由来する供給不足時に、我が国に重大な影響が生じる恐れがある。
- 『経済安全保障推進法』は、国民の生存や国民生活・経済活動にとって重要であるなどの4つの要件を満たす物資を「特定重要物資」に指定し、サプライチェーンの強靱化を図る制度を設けている。
- 2022年12月23日、抗菌薬、肥料、永久磁石、工作機械・産業用ロボット、航空機の部品、半導体、蓄電池、クラウドプログラム、可燃性天然ガス、重要鉱物、船舶の部品の11物資を「特定重要物資」に指定する『経済安全保障推進法の施行令(政令)』を施行した。(これら物資の安定供給確保の所要経費として、2022年12月2日に成立した「令和4年度第2次補正予算」で、計1兆358億円が措置された。)
- 2024年2月2日、サプライチェーンの更なる強靱化のため、先端電子部品(コンデンサー、高周波フィルタ(ろ波器))を「特定重要物資」に追加指定するとともに、既に指定されている重要鉱物にウランを追加する『政令』を施行した。
- 2023年4月14日以降、12分野における安定供給確保のための計画(供給確保計画)が、計91件認定されている(2024年8月31日時点。直近の認定は2024年8月30日)。
- また、サプライチェーン強靭化のための所要経費として、「令和5年度補正予算」で計9,172億円、「令和6年度予算」で計2,300億円が、それぞれ措置された。(これまでに措置したサプライチェーン強靭化予算の総額は、2兆1,830億円)
2.『経済安全保障推進法』に基づく「経済安全保障重要技術育成プログラム(K Program)」の推進
(経緯)
- 2022年9月16日 「経済安全保障推進会議・統合イノベーション戦略推進会議合同会議」において『研究開発ビジョン(第一次)』を決定し、支援対象として27の重要技術を選定
- 2022年9月30日 『特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針』を閣議決定
- 2023年2月8日 「経済安全保障重要技術育成プログラムに係るプログラム会議(第4回)」において、今後の『研究開発ビジョン』の策定に向けた議論のキックオフ
- 2023年3月27日 プログラムとして最初の採択公表(NEDO・3件)
- 2023年8月28日 「経済安全保障推進会議・統合イノベーション戦略推進会議合同会議」において『研究開発ビジョン(第二次)』を決定し、支援対象として新たに23の重要技術を追加
- 2023年12月8日 『研究開発ビジョン(第二次)』に基づく最初の公募開始(NEDO・4件)
- 2024年4月5日 研究開発ビジョン(第二次)に基づく最初の採択公表(NEDO・1件)
- 2024年8月27日 「経済安全保障重要技術育成プログラムに係るプログラム会議(第9回)」において、初めてとなる研究開発の進捗報告を実施
(概要)
- 科学技術・イノベーションが国家間の覇権争いの中核を占める中、先端的な重要技術の研究開発やその成果活用が我が国の国民生活や経済活動にとって重要であるのみならず、中長期的に我が国が国際社会で確固たる地位を確保し続ける上で必要不可欠。先端的な重要技術については、諸外国と伍する形で研究開発を進めることが求められている。
- このため、『経済安全保障推進法』は、将来の国民生活や経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術を「特定重要技術」に指定し、国が資金を確保して研究開発や成果の活用に向けて強力な支援を行う制度を設けている。
- 2022年9月に決定した「K Program」の支援対象となる重要技術を示す『研究開発ビジョン(第一次)』に基づき、具体的な研究開発構想を作成し、2023年3月には、プログラムとして最初の3事業(宇宙・海洋領域)を採択した。2023年7月には、これら3事業について、『経済安全保障推進法』に基づく「指定基金協議会」を開催した。
- 2023年2月より、次の研究開発ビジョン策定に向けた議論を開始し、2023年8月28日の「経済安全保障推進会議・統合イノベーション戦略推進会議合同会議」において『研究開発ビジョン(第二次)』を決定し、支援対象として新たに23の重要技術を追加した。
- さらに、食料安全保障に資する取組の追加について継続的に検討を進めているところ。(プログラム会議(第9回)において、バイオ分野に知見のある有識者を研究開発ビジョン検討ワーキンググループ構成員に追加し、追加すべき支援対象技術について検討を進める。)
- 今後も、「指定基金協議会」(2024年8月末時点で計13件設置)を通じた国による伴走支援の実施を含め、着実に研究開発を推進していく。
- なお、「K Program」のための経費として、令和3年度補正予算と令和4年度第2次補正予算において、計5,000億円を確保している。
3.『経済安全保障推進法』に基づく「基幹インフラ役務の安定提供確保」に関する制度の運用
(経緯)
【制度運用に向けた準備】
- 2023年4月28日 『特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本指針』を閣議決定
- 2023年8月1日 『経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令』を閣議決定
- 2023年11月1日 法の一部施行(特定社会基盤事業等、特定社会基盤事業者の指定基準、特定重要設備)
- 2023年11月16日 特定社会基盤事業者の指定(計210者(当時)、2024年8月31日時点では212者)
- 2023年11月17日 法の施行(重要維持管理等、届出事項)
- 2024年5月17日 制度運用開始
【対象事業の追加】
- 2024年2月27日 特定社会基盤事業に一般港湾運送事業を追加する『経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案』閣議決定
- 2024年5月10日 『経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律』成立
- 2024年5月17日 『経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律』公布
(概要)
【制度運用に向けた準備】
- 基幹インフラ事業を規律するいわゆる『業法』は、外部から行われる妨害行為を未然に防止することを目的としておらず、設備導入、維持管理の委託といった通常の事業活動に起因するリスクに対して、十分な対応がとれない恐れがある。
- 『経済安全保障推進法』において、一定のインフラ事業者が設備の導入や維持管理の委託等を行う前に、政府が当該設備の導入等に伴うリスクを事前に審査し、リスクが大きければ低減・排除するべく、事業者に勧告・命令することができる仕組みを創設した。
- この制度は規制措置となるため、国家及び国民の安全と自由な経済活動のバランスに留意し、規制対象を真に必要なものに限定するとともに、事業者からの意見の実態等を十分に踏まえて制度を整備し、運用していくことが重要である。
- 2023年4月28日には『基本指針』を閣議決定し、「制度の基本的な考え方」「特定社会基盤事業者の指定基準」「特定重要設備を定めるに当たっての考え方」「届出事項や審査の考慮要素」などを示した。
- 2023年8月1日には、『経済安全保障推進法の施行令の一部を改正する政令』を閣議決定し、制度の対象として指定可能な事業者の事業の範囲として、『経済安全保障推進法』で定めた、電気、ガス、水道などの14事業のうち、役務の安定的な提供に支障が生じた場合に、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものを、「特定社会基盤事業」として定めた。
- 2023年8月9日には、特定社会基盤事業者の指定基準や特定重要設備等を具体的に定める『省令』を、関係省庁において公布した。
- 2023年11月1日には、特定社会基盤事業等を定める『政令』及び特定社会基盤事業者の指定基準や特定重要設備を具体的に定める『省令』が施行された。
- 2023年11月16日には、関係省庁において、特定社会基盤事業者を指定したほか、特定社会基盤事業者の届出事項等に関する『省令』が公布された。
- 2023年11月17日には、関係省庁において、指定された特定社会基盤事業者が告示され、特定社会基盤事業者の届出事項等に関する『省令』が施行された。
- その後、技術的な解説の作成・公表を随時実施するなど、制度の周知・広報を積極的に行い、2024年5月17日、特定社会基盤事業者の指定から6か月間の経過措置期間を経て、制度の運用を開始した。
【対象事業への一般港湾運送事業の追加】
- 2023年7月に発生した名古屋港コンテナターミナルにおけるサイバー攻撃によるシステム障害を受け検討を行った結果、2024年2月27日、「一般港湾運送事業」を特定社会基盤事業に追加するための『経済安全保障推進法』の一部改正法案を閣議決定の上国会に提出し、同年5月10日に成立、17日に公布された。
4.『経済安全保障推進法』に基づく「特許出願の非公開」の制度の運用
(経緯)
- 2023年4月28日 『特許出願の非公開に関する基本指針』を閣議決定
- 2023年8月1日 『経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令』を閣議決定
- 2023年12月18日 内閣府令(保全審査手続、適正管理措置等)・共同府省令(一次審査手続、外国出願事前確認手続等)を公布するとともに、制度の内容を解説するガイドラインやQ&A(制度・損失補償)公表
- 2024年5月1日 制度運用開始
(概要)
- 我が国の特許制度は、特許出願人に対して一定期間独占権を付与して発明の保護を図りつつ、特許出願された発明を一律に公開して、第三者による改良技術の開発促進、重複する研究開発の排除などにより発明の利用を図り、もって産業の発達に寄与することを基本としている。
- 他方、従来、安全保障上拡散すべきでない発明であってもその内容が公開されるため、拡散を懸念する発明者は特許出願を諦めざるを得ない状況にあった。諸外国では多くの国が安全保障上の理由で特許出願を非公開とする制度を有している。
- このため、『経済安全保障推進法』において、特許制度の基本的な枠組を維持しつつ、公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずる恐れが大きい発明が記載されている特許出願につき、出願公開等の手続を留保するとともに、その間、必要な情報保全措置を講じる制度を整備した。
- 保全指定をすると、産業の発達に様々な影響が生じ得るため、我が国の安全保障上極めて機微な発明であることを前提としつつ、経済活動やイノベーションへの影響も踏まえて、安全保障を確保するため合理的に必要と認められる限度において行わなければならない。また、特許出願人が手続を円滑に行うことができるように配慮することも必要である。
- 2023年4月28日には『基本指針』を閣議決定し、「非公開の対象となる発明の考え方」「保全審査の手続における留意点」などを示した。
- 2023年8月1日には、『経済安全保障推進法の施行令の一部を改正する政令』を閣議決定し、保全審査の対象となる、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野を、「特定技術分野」として定めるとともに、非公開とした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きいと認められる技術の分野、及びそのような技術の分野であっても審査に付すべき発明の要件(「付加要件」)を定めた。
- 2023年12月18日には、内閣府令を公布し、保全審査において特許出願人の意見を聴取する旨や、保全対象発明の適正管理措置として、組織的・人的・物理的・技術的な情報管理に関する措置の具体的内容等を定めるとともに、内閣府・経済産業省の共同府省令を公布し、第一次審査や外国出願事前確認における特許庁に対する手続等を定めた。また、制度そのものや発明を非公開とされた場合に生じる損失の補償について解説したQ&A、保全対象発明の適正管理措置の具体的な内容について解説するガイドラインもあわせて公表した。
- その後、説明会を随時実施するなど、制度の周知・広報を積極的に行い、2024年5月1日、制度の運用を開始した。
5.「経済安全保障版セキュリティ・クリアランス制度」の創設に向けた取組
(経緯)
- 2022年12月16日 『国家安全保障戦略』を閣議決定
- 2023年2月14日 「第4回経済安全保障推進会議」の開催
- 2023年2月22日 「第1回経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議」を開催。6月6日に中間論点整理を取りまとめ。2024年1月17日に最終とりまとめ案を公表。(第2回:2023年3月14日、第3回:3月27日、第4回:4月7日、第5回:4月25日、第6回:5月29日、第7回:10月11日、第8回:11月20日、第9回:12月20日、第10回:2024年1月17日)
- 2024年2月27日 『重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案』閣議決定
- 2024年5月10日 『重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律』成立
- 2024年5月17日 『重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律』公布
- 2024年6月26日 「第1回重要経済安保情報保護活用諮問会議」を開催(第2回:7月31日、第3回:8月29日)
(概要)
- 安全保障の概念が防衛や外交という伝統的な領域から経済・技術の分野に拡大している。安全保障のための情報能力の強化が一層重要となる中で、経済安全保障分野においても、「セキュリティ・クリアランス」を含む情報保全の更なる強化を図る必要がある。
- 「セキュリティ・クリアランス」とは、国家における情報保全措置の一環として、政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報に対して、アクセスする必要がある者のうち、情報を漏らすおそれがないという信頼性を確認した者の中で取り扱うとする制度。
- 経済界からも、同盟国・同志国の政府調達などとの関係で、国際的に通用する「セキュリティ・クリアランス制度」の創設について要望が寄せられた(経団連、経済同友会、各企業等)。
- 日本企業が海外でのビジネスチャンスを拡大していく上でも、「セキュリティ・クリアランス制度」は有用である。
- 従来のセキュリティ・クリアランス制度である『特定秘密保護法』では、経済安全保障に関する情報が必ずしも明示的に保全の対象になっていないこと、また、いわゆるトップシークレット、シークレットに次ぐ、コンフィデンシャル相当の情報類型がカバーされていないといった課題が指摘されていた。
- 2023年2月14日の「第4回経済安全保障推進会議」において、岸田総理から、「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度のニーズや論点等を専門的な見地から検討する有識者会議を立ち上げ、今後1年程度をめどに、可能な限り速やかに検討作業を進めること」との指示があった。
- 2023年2月22日に「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議」を設置し、第1回会合を開催。5月まで月1~2回のペースで、民間企業からニーズや要望等を直接ヒアリングするなど、制度の方向性について検討を重ね、6月6日に『中間論点整理』がとりまとめられた。
- 2023年10月に有識者会議を再開し、『中間論点整理』をベースに制度の具体的な方向性について議論し、2024年1月19日には有識者会議の委員の検討の最終的な結果をとりまとめた『最終とりまとめ』を公表した。
- 『最終とりまとめ』も踏まえ検討を進め、2024年2月27日、『重要経済安保情報保護活用法案』を閣議決定し、国会に提出した。衆参両院合計で44時間以上の審議を経て、同年5月10日、同法が成立し、17日に公布された。これにより、「経済安全保障版セキュリティ・クリアランス制度」の創設が国会で認められた。
- 『重要経済安保情報保護活用法』を実施に移すための『政令』及び『統一的な運用を図るための基準(運用基準)』の案などを有識者に議論いただく場として、2024年6月10日、『重要経済安保情報保護活用諮問会議』を開催することを決定し、同月26日、第1回の会議を開催。同会議において岸田総理から、『運用基準』について「できるだけ速やかに、年内をめどに策定することを目指していきたい」との政府としての決意が示されており、有識者のご意見を伺いながら検討を進めていくこととしている。
- これらのルールの策定や、制度の実施体制の整備により、実効的な運用を確保し、諸外国に通用する制度としていく。
6.「安全・安心に関するシンクタンク」の本格的な設立準備
(経緯)
- 2022年11月29日 「安全・安心に関するシンクタンク設立準備検討会」を開催(計5回開催)
- 2023年4月7日 「安全・安心に関するシンクタンクの基本設計」を取りまとめ
- 2023年12月13日 「安全・安心シンクタンク運営ボード」を開催(2024年8月までに計5回開催)
(概要)
- 科学技術・イノベーションは、激化する国家間の覇権争いの中核を占め、安全・安心な社会の構築の観点から、サイバー空間におけるセキュリティの確保、新たな生物学的な脅威への対応、宇宙・海洋分野等の安全・安心への脅威への対応、また、これらの領域を横断するリスク・脅威・危機への対応としても、国家の命運を握る生命線となりつつある。
- 我が国においては、安全・安心の実現のための重要な諸課題に対応し、科学技術の多義性を踏まえつつ、総合的な安全保障の基盤となる科学技術力を強化する観点から、これまで、脅威等に対応する技術を「知る」、技術を「育てる」、育てた技術を社会実装し「生かす」、技術の流出を防ぎ「守る」ための様々な取組みを行ってきた。
- このうち「知る」については、第6期科学技術・イノベーション基本計画等に基づき、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局において、「安全・安心に関するシンクタンク」の本格的な設立準備を進めている。
- 安全・安心に関するシンクタンクは、国民生活、社会経済に対する脅威の動向の監視・観測・予測・分析、国内外の研究開発動向把握や人文・社会科学の知見も踏まえた課題分析を行うことを目的としている。
- これまでの取り組みとしては、多角的に立ち上げるべきシンクタンク像を明確化するため、2022年11月から2023年3月にかけて、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局において、外部有識者による「安全・安心に関するシンクタンク設立準備検討会」を開催し、2023年4月には、「安全・安心に関するシンクタンクの基本設計」を取りまとめた。
- 2023年度以降、この基本設計に基づいて、本格的なシンクタンク設立準備を進めているところ、高度な調査・分析人材の育成とネットワーク化や先行的な調査研究といった、シンクタンクのコア機能として必要な取組等については、委託事業を活用しながら継続的かつ発展的に実施している。
- こうした設立準備作業について、進捗を確認するとともに、外部有識者から必要な助言をいただくため、2023年12月から「安全・安心シンクタンク運営ボード」を開催している。
- 今後も引き続き、外部有識者の知見も活用しながら、シンクタンクの最適な組織形態の在り方等について具体化に向けた検討を更に深めるとともに、調査・分析手法の確立や人材の確保・育成、調査研究ネットワークの構築等の取組を着実に進めていく。